頭痛に対する評価や扱い方のご質問
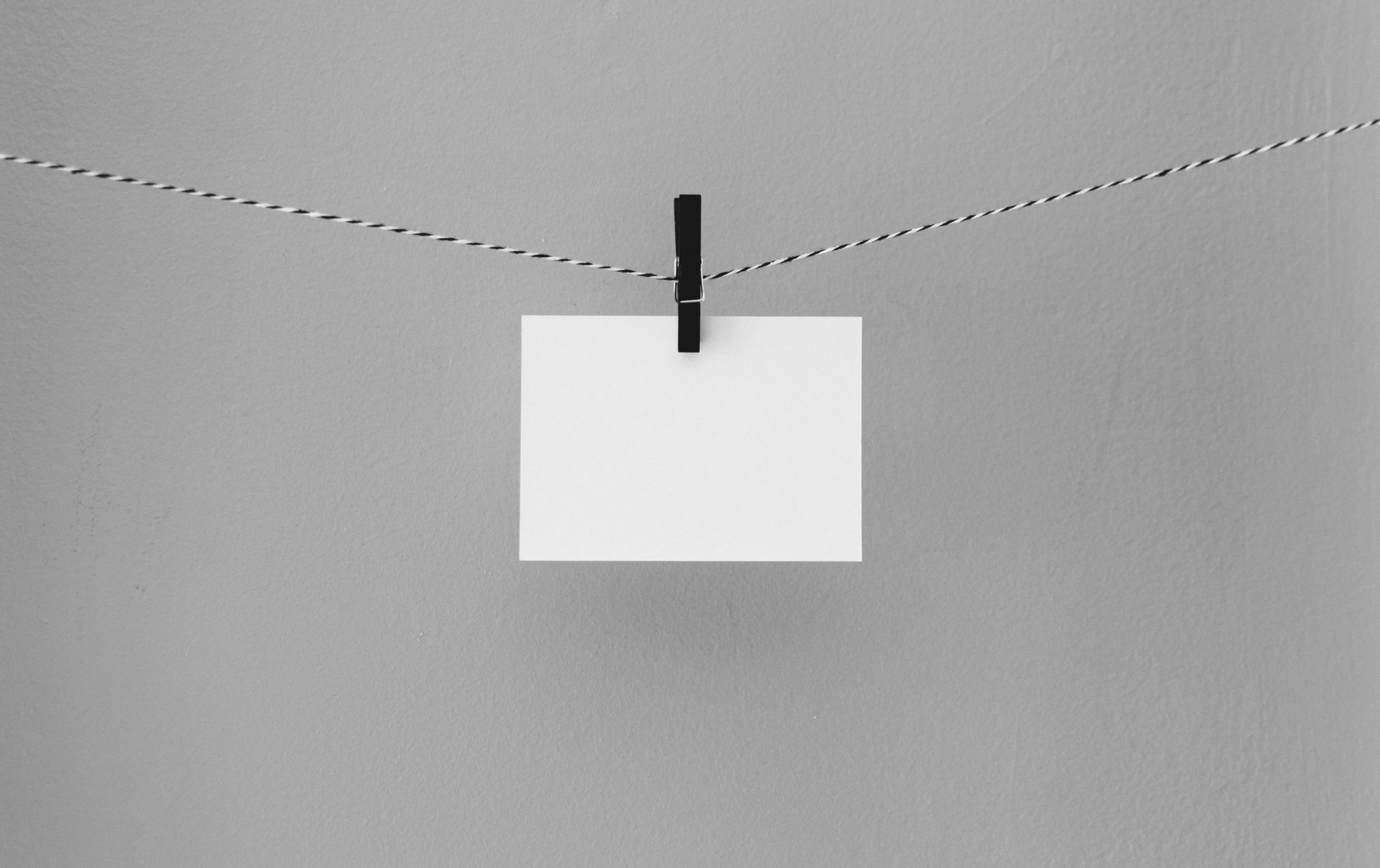
整体院で勤務しています。頭痛をご相談頂くことがありますが、頚部や背中の緊張を緩和させたりとトライしてみますが、むしろ頭痛をその場で悪化させてしまう場合もありました。
勤める整体院では、頭痛の患者さんを集客しており、ご相談を多く頂きます。しかし、正直どのように扱ってよいのかわかっていません。
頭痛の方を見る際の扱い方のアドバイスを頂ければと思います。
Ishikawa Case Advice
頭痛は扱う機会が非常に多い症状の一つですので基本的な事項を理解しておかなければなりません。
施術によって改善が見込める頭痛もあればあまり手を加えない方がよい頭痛もありますし、患者さんに適切な指導ができれば根本的な解決ができたり、根治が難しい頭痛でも軽減させたり頻度を減らせるものです。
頭痛診療ガイドライン
まずは一度、国際頭痛学会が出版している頭痛診療ガイドラインを参照して下さい。
国際頭痛学会は数えきれないほどの多くの頭痛の種類を分類し、それぞれの特徴から可能な対処方法や治療ガイドラインを提唱しています。
一次性頭痛と二次性頭痛

頭痛には大きく分けて「一次性頭痛:The primary headache」に属する頭痛と、「二次性頭痛:The secondary headache」に属する頭痛があります。
一次性頭痛とは一般的に起こりやすい頭痛、珍しくない頭痛の範疇で、緊急性の低い頭痛です。
一次性頭痛とは
どんなに激しい頭痛であったとしても命に関わることはないのが一次性頭痛です。
一方で二次性頭痛は緊急性のある頭痛、患者数の少ない稀な頭痛です。
二次性頭痛とは
二次性頭痛に関しては、その詳細な内容よりも頭痛のレッドフラッグサインを理解しておき、緊急性が疑われる場合や専門医に速やかに相談すべき頭痛であることを察知できるよう学習しておく必要があります。
頭痛は問診で決まる
『頭痛に関する診断の8割~9割は問診で決まる』と言われています。
他の障害や疾病に関しては7割程度と言われていますが、頭痛にはそれだけ問診による情報収集が重要だということです。
各頭痛の特徴や臨床像を理解した上で、的確なヒアリングにより鑑別を行ってください。
一次性頭痛の種類

一次性頭痛について、その内容をしっかりと理解しておきべき頭痛が以下の通りです。
筋緊張性頭痛
筋緊張性頭痛は「緊張性頭痛」「筋・筋膜緊張性頭痛」などいくつかの呼び方があります。ここでは「Tension Type HA:TTH」=筋緊張性頭痛で進めていきます。
TTHは頭や筋肉の緊張が頭痛の原因になっているものを指します。
根本的にはさらにその筋緊張を招いている原因を追及する必要がありますが、この場合の頭痛の正体は関連痛というものです。
頭痛とトリガーポイント
筋肉の過緊張によりトリガーポイントと呼ばれる筋硬結が生じ、このポイントから頭部もしくは顔面などに痛みが拡散する場合があり、これを関連痛(Radiational pain)といいます。
頭頚部に関わる各筋肉のトリガーポイント好発部位と対応する関連痛ゾーンをしっかりと理解しておく必要があります。
また関連痛の出現はなくとも、頭頚部のいくつかの筋肉に過剰な緊張が続き、極端な血行不良や神経過敏な状態に陥れば、それ自体が頭痛症状を引き起こす原因にもなります。
TTHの頭痛の感覚は圧迫感・緊迫感・頭重感と言われていますが、
頭痛の感覚を聴く
患者さんに『感じている頭痛は圧迫感ですか?緊迫感ですか?』と尋ねても、患者さんにはわかりませんので、
『どんな頭痛の感覚ですか、例えばズキズキとかガンガンとか、自由な表現でいいので言えますか?』
という質問の仕方が必要です。
患者さんがうまく説明できない時は、いくつか選択肢をあげて該当するものを選んでもらうといいです。
その際、拍動痛といって脈を打つ感じで『ドクドク』という表現が出たら、TTHよりも片頭痛に該当する表現ですので、鑑別上のポイントになります。
またTTHは筋肉の疲労が蓄積してくる夕方や仕事終わり頃に出現することが多く、
筋肉に対する血流が改善されるような入浴や適度な運動で症状が緩和することが比較的多いのですが、頭痛薬や鎮痛薬は一般に片頭痛には効果を示しますがTTHにはあまり効果を示さないことが多いようです。
TTHの症状が酷い場合は吐き気を伴うことがありますが、実際に嘔吐してしまうまでには発展しないことが殆どのようです。また片頭痛では光や音に敏感な状態になるのですが、TTHはそれ程過敏にはならない傾向にあります。
片頭痛
慢性的な頭痛=片頭痛という解釈が一般的かと思いますが、実際のところは片頭痛には片頭痛の診断基準と特徴があり、筋緊張性頭痛とは異なるものです。
「肩こりから片頭痛になるのよね」
というのは、正しくは肩こりが原因となる頭痛は筋緊張性頭痛で片頭痛ではありません。
大脳の浮腫み
片頭痛の明確な原因とメカニズムは様々な仮説が立てられ、医学的に研究が行われていますが、今のところ決定的なものは見つかっていませんが、片頭痛が起きている最中には大脳の浮腫(むくみ)を生じることが分かっています。この浮腫の状態は脳内の血行不良ではなく、むしろ「血流過多」状態を伴います。
片頭痛の傾向
片頭痛の傾向と特徴を見ていきます。
まず若い年齢で発症することが殆どで、学生時代にはもう頭痛が定期的にあったというのが殆どです。一方で高齢になると片頭痛に該当するものは極端に減少する傾向にあります。
男女差では圧倒的に女性に多く中でも低血圧な方に多いとされています。
片頭痛は起床時頭痛と呼ばれるほどに目が覚めた時に感じることが多いという特徴があります。
また頭痛の性質として「拍動性」であることが特徴です。
これは筋緊張性頭痛とは異なる点であり鑑別上重要です。片頭痛と言えど、症状が両側に出る場合も少なくなく、個人差はありますが、定期的に出現してくるというのも片頭痛の特徴です。
また両親に片頭痛持ちがいると遺伝しやすいという統計もありますので、問診の際に確認してみてください。中でも母親からの遺伝が強い傾向にあります。
片頭痛の最大の特徴ともいえるのが閃輝暗点(せんきあんてん)です。頭痛が起こる前の前兆サインです。眩しい光が目の前の現れ、それが次第に黒い暗点に変化していくという視覚に現れる事象です。これは筋緊張性頭痛では起こりえない、片頭痛だけに現われることのある徴候です。
片頭痛が増悪する要素のすべてに言えることは、「頭蓋内の血流が増す行為」と言えます。週末に増悪しやすいのも、リラックスした状態で血流が増し、片頭痛が出現すると考えられています。
小児周期性症候群(CPS)とは
周期性嘔吐症、腹部片頭痛、小児良性発作性めまいという3つに該当する症状を持つ小児を小児周期性症候群といいます。3つ全てでなく、1つでもCPSに該当する場合もあります。
このCPSに該当する小児は思春期から成人を迎える間をピークに片頭痛を発症する可能性が極めて高くなるとされています。
- ・周期性嘔吐症:頻繁に突然嘔吐してします小児の状態
- ・腹部片頭痛:頻繁にお腹が痛いという小児の状態
- ・小児良性発作性めまい:気持ちがわるい、めまいがすると頻繁に訴える小児の状態
大後頭神経絞扼障害(後頭神経痛)
末梢神経は筋肉の中を貫通して走行することが少なくありません。
筋肉の過緊張によって神経が絞扼されれば、その絞扼点より遠位の神経は痺れや機能異常を呈してきます。
大後頭神経は頭半棘筋と上部僧帽筋に絞扼される可能性を持っています。
頚部の位置により、痺れが後頭部に出現したり、シャンプーをする時に後頭部の感覚が明らかにおかしいなどの症状を訴えることがあります。
絞扼の原因となる頭半棘筋や上部僧帽筋の過緊張の原因を探り、解消することができればこの神経症状は解決されます。
混合性頭痛
MgとTTHの両方の性質を持ち合わせ、どちらかの頭痛ということでなく、両方の頭痛を持ち合わせている場合をいいます。平日にはTTH、週末にはMgに苛まれるという方も少なくありません。
頚椎原性頭痛
Cervicogenic-headacheと呼ばれます。これは後頭下筋群のうち、大後頭直筋・小後頭直筋と頭蓋内の硬膜を連結している結合組織(筋硬膜橋:Connective-Tissue-Bridge)が関与している頭痛です。
何らかの原因で後頭直筋が過緊張を起こし、CTBを介して頭蓋内硬膜が引っ張られて、頭痛が出現するというものです。
意味合いとしては、筋緊張性頭痛に含まれるものですが、硬膜が関与するものとして、国際頭痛分類ガイドラインの中でも別途説明されている頭痛です。
群発性頭痛:Cluster-headache
一次性頭痛の中で最強の頭痛です。症状の強さは精神を崩壊させるほどの頭痛と言われ、痛みのために自傷行為をするケースも少なくないといいます。
ハリーポッターの主役として有名なダニエル・ラドクリフがこの群発性頭痛を患い闘病したことが有名です。
この頭痛は頭痛といっても眼と眼の周囲の痛みが主な症状で、軽い痛みではなく、とにかく強烈な痛みとのことで、他の頭痛との鑑別は不要かと思います。
有効な治療法などは今のところ見つかっていませんが、高濃度の酸素吸入などで痛みを減らせることがあると言われています。
頭痛の禁忌症サイン

頭痛のレッドフラッグサインをしっかりと覚えておく必要があります。
つまり一次性頭痛ではなく、二次性頭痛の可能性があり緊急性がある場合があるためです。
感じたことのない頭痛、突然始まった頭痛、強すぎる頭痛、どんどん悪化していく頭痛、高熱を伴う頭痛、精神異常を伴う頭痛です。
上記のような場合、「何かおかしい感じがする」という患者さん自らの感覚があるかと思います。
施術を提供するだけが我々の仕事ではありません。
患者さんにとってベストな選択をするのが仕事ですので、危険性を感じた場合は速やかに医療機関を受診するよう説明してください。
頭痛の評価のまとめ
今回は頭痛の評価、頭痛の種類についてまとめました。
頭痛は鑑別がとても重要です。
正しい知識、そして対処法を学んでいきましょう。
IMIC学長
石川貴章
皆様からのご質問の受付

ISHIKAWA CASE ADVICEでは皆様からの臨床におけるご質問などを受け付けております。
・難しいケースで対応できない
・どのように検査して良いかわからない
・闇雲に施術をしている
・マニュアル通りの施術で患者様が良くならない
等、日々の臨床では様々なお悩みがあるかと思います。
あなたが困っている事、私にお教えください。
ブログや動画でアドバイス致します。
ラインからのご質問
公式ラインはこちら
ご登録後、
・お名前
・お悩み事
をご記入の上、ご送信下さい。
IMIC公式youtube

youtubeでは日々の臨床に役立つIMICのYoutube整体教室を毎日アップロードしております。
動画の内容は、テクニックや知識の極一部です。テクニックはスポットだけで使用するのではなく、
患者様の症状の鑑別、そして詳細な身体の分析を行い、患者様がより早く改善するように行うものです。
参考程度の動画だという事は予めご了承ください。
頸部の評価の動画・熟練者の手技の身体の使い方の動画
石川貴章。IMIC学長。石川カイロプラクティック総院長。RMIT大学カイロプラクティック学科日本校の臨床テクニック、臨床学の元常任講師。



